
Webサイト制作を受注した後の流れはどうすればいい?
トラブルにならないように案件を進行したいけど不安

Webサイト制作を始める前に、要件定義が必要です
何をどこまで決めたらいいか分からない方向けに、
具体的な項目とポイントを解説します!
初めてWebサイト制作を受注した際、
打ち合わせで何を決めたらいいか悩む人も多いでしょう。
最初に要件をまとめないと、進行途中で認識違いが起きて
トラブルに発展する可能性があります。
今回は、Webサイト制作を数多く受注してきた僕が、
要件定義書に必要な項目とポイントを解説します!
「これからWebサイト制作の案件を獲得したい」
「初案件を獲得したけどどう進めたらいいか分からない」
という人はこの記事の要件定義のまとめ方を参考にしてください!
要件定義とはWebサイトの仕様を決めること
要件定義とは、Webサイトの仕様を決めることです。
Webサイトの機能や概要などの具体的な内容だけではなく、
スケジュールや費用なども要件定義で言語化します。
制作前にプロジェクトの詳細を固めることで手戻りを防ぎ、
かつクライアントの要望も整理できるため重要な業務となります。
期限内にクライアントの要望を実現するためには、
事前にクライアントとの打ち合わせを行い
要件定義をまとめてから制作を始める必要があります。
要件定義をまとめたものを要件定義書といい、
関係者に共有するために用います。
Web制作における要件定義の進め方4ステップ
Web制作における要件定義は、以下の4ステップで進めます。
- クライアントへヒアリングを行う
- 方向性を決める
- クライアントの合意を得る
- 要件定義書を作成する
要件定義で1度決めたものは基本的には変更しないので、
しっかりと打ち合わせを行って決定することが大切です。
1.クライアントへヒアリングを行う
まずはクライアントへヒアリングを行い
現状の課題やWebサイトに必要な機能を確認します。
クライアントの求めるWebサイトを制作するためには、
ヒアリングの段階で漏れなく情報を集める必要があります。
Webサイトそのものだけではなく、
スケジュールや予算についてもヒアリングしましょう。
ヒアリングは後々の工程を左右する重要な業務なので、
丁寧に行ってください。
具体的なヒアリングのやり方が分からない場合は、
以下の記事でヒアリングのやり方を徹底解説しています。
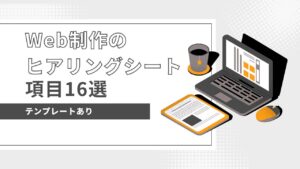
2.方向性を決める
実施したヒアリングをもとに、
どのような方向でWebサイトを制作するのかを決めます。
例えば、問い合わせの増加を求めているクライアントには、
リードを獲得できるWebサイトを制作する必要があります。
担当者が設定しやすいような問い合わせフォームの最適化や
ユーザーがクリックしやすい適切なバナーの設置など、
具体的な方向性を決めましょう。
上記のようにWebサイト制作の具体的な方向性を提案し、
課題を解決できるようにすることが重要です。
3.クライアントの合意を得る
上記で決定した内容で問題がないか、
必ずクライアントへ確認を取り合意を得ることも大切です。
合意を形成する際は、
関係部署ごとに確認を取ったり調整したりしましょう。
各部署全ての疑問や不満を解決するのは難しいですが、
個別に対応することで「自分の話を聞いてくれている」
という認識を持ってもらえます。
丁寧に合意を得てお互いに信頼関係を築いておくと、
Webサイト制作に対して前向きに対応してもらえるようになります。
Webサイト制作に対する知識のないクライアントには、
ワークショップを開くのもおすすめです。
Webサイト制作の担当部署だけでなく、
関連する部署にもワークショップに参加してもらいましょう。
ワークショップを通じてサイト制作へ関心を持ってもらい、
要件定義が再検討されるリスクを低減できます。
複数の部署とやりとりするのは時間がかかりますが、
丁寧に合意を得ることでその後のサイト制作が
スムーズに行えるようになります。
4.要件定義書を作成する
合意形成が成立した後は、要件定義書を作成します。
要件定義書はプロジェクトの指針となるだけでなく、
制作中に迷いが生じた際の判断基準にもなります。
例えば、部署間で意見が対立したときや選択をせまられた際に、
要件定義書を参照することで適切な意思決定が可能となります。
そのため、要件定義書には可能な限り詳細な情報を記載しましょう。
これにより、プロジェクトの全体像を把握しやすくなり、
関係者や部署間の認識を統一できます。
フリーランスの場合は、要件定義書ではなく
ヒアリングシートを共有することでも対応可能です。
クライアントに要件定義書の有無を確認し、
どちらを提出するか判断しましょう。
Web制作の要件定義に必要な項目9選
要件定義の際に特に欠かせない項目を9つ紹介します。
- Webサイト制作の背景・目的
- Webサイトの構成
- OSとブラウザの定義
- Webサイトのデザインイメージ
- 必要な機能
- 対応範囲
- 制作スケジュール
- 予算
- 納品方法
- 運用保守の有無
どれか1つ欠けてもWeb制作の進行に影響が出てしまうので、
具体的な内容を解説します!
Webサイト制作の背景・目的
要件定義書の背景には、主に以下の3つの項目を記載します。
- 制作の目的
- 現状の問題点や課題
- リニューアルの対象範囲
なぜWebサイト制作やリニューアルを行うのか、
その目的を明確に記述します。
例えば、企業イメージの刷新や売上増加などが目的になるでしょう。
目的が決まったら現状の問題点や課題を整理し、具体的に記載します。
Webサイトのアクセス解析データやアンケート結果、
競合他社の調査結果などにもとづいた分析結果を盛り込みます。
Webサイトのリニューアルでは、
対象となる範囲も決めておくことが大切です。
リニューアルするページやコンテンツ、
デザインやUI、追加する機能面など、具体的に指定します。
また、要件定義書で使用される専門用語や略語は、
その意味の解説を記載しておくことが重要です。
用語の定義を記載しておくことで
途中から参加するメンバーもスムーズに内容を理解し、
プロジェクトに合流しやすくなります。
プロジェクトの全体像や目的を関係者間で共有し、
意識を統一することが円滑なWeb制作の進行に欠かせません。
Webサイトの構成
Webサイト構成の項目では、
Webサイトのサイトマップを定義します。
サイトマップとは、サイト内の階層構造や
ページ間のつながりを視覚的に表現した図です。
サイトマップでは、主に以下の内容を定めます。
- サイトに含まれる項目(セクション)
- 各セクションに属するページ
- 各ページのURL構造
サイトマップを作成することでWebサイト全体を把握し、
ページ間の導線を最適化できます。
開発者にとってこのサイトマップは、
サイト構築の指針となる重要な設計図になります。
OSとブラウザの定義
また、Webサイト別ごとに、
対応するOSとブラウザを明確に定義することが重要です。
Webサイトはさまざまな環境で閲覧されるため、
すべての環境に対応することは現実的ではありません。
そのため、ターゲットユーザーの利用環境を調査し、
優先度の高い環境に絞って対応することが求められます。
PC向けサイトの場合、対象OSやブラウザの定義
は以下のようになります。
- 対象OS:Windows 10以降、macOS 10.15以降など
- 対象ブラウザ:Google Chrome、Microsoft Edge、Safariなど
スマートフォン向けサイトの場合は、以下のとおりです。
- 対象OS:iOS 14以降、Android 10以降
- 対象ブラウザ:Google Chrome、Safari
対象OSやブラウザを明確に定義することで、
開発工数の見積もりやテスト計画の立案がしやすくなります。
また、ユーザーに対しても推奨環境を明示することで、
最適な閲覧環境を提供できます。
Webサイトのデザインイメージ
Web制作ではどのようなデザインのサイトを制作するか、
イメージやテーマカラーなどを決めます。
テキストの配置や画像の使い方など、
デザインに関わる要素を具体的に設定します。
デザインを決める際は、
参考になるWebサイトを設定しておくと
クライアントとイメージの相違がなくなりますよ!
デザインと同時にWebサイトのテーマも決めましょう。
サイトを通じて伝えたいメッセージや価値観をまとめ、
デザインイメージに反映させるとさらに良くなります。
「高級感」「親しみやすさ」などのサイトテーマを設定し、
デザインに組み込むとよりデザインを決めやすくなります。
必要な機能
必要な機能には、Webサイトに実装したい機能を記載します。
実装する機能の例としては、以下のようなものがあります。
- パンくずリスト
- ナビゲーション
- お問い合わせフォーム
- ブログ
- サイト内検索
最初に決めたWebサイトの目的に応じて、
どの機能を追加していくか決めていきましょう。
機能の数や内容によって、
実装する際の業務量も異なってきます。
公開後に新たな機能を追加するのは
クライアントにとっても手間と費用がかかるので、
漏れなく要望を確認しておくことが大切です。
対応範囲
要件定義では、どこまでを対応するか決めることも必須です。
Web制作と一括りで言っても、
業務内容には以下のようなものが含まれます。
- デザイン・コーディング
- ロゴの制作
- Webマーケティングなど
対応範囲をきめておかないとクライアントと認識がずれてしまい、
「Webマーケティングは対応してくれないんですか?」
などとクレームにつながる可能性があるので注意しましょう。
また、進行途中で「ここまでやってもらえませんか?」
などと言われても、要件定義で対応範囲を決めておけば
断ったり追加費用で対応したり選べます。
対応範囲を曖昧にしてしまうと、
想定外の業務まで担当する可能性が出てくるので
忘れずにクライアントに合意を得てから明記しましょう。
制作スケジュール
Web制作を受注する際は、いつから始めて
いつまでに納品するかスケジュールを設定します。
その際、公開から逆算して
以下の業務ごとにスケジュールを設定しましょう。
- Webサイト設計
- デザイン制作
- コンテンツ制作
- コーディング
- システム開発
- 検証と修正
- 公開
それぞれのスケジュールは想定外のトラブルを考慮して
余裕を持った期日を設定しておくと焦らずに案件にコミットできます。
クライアントの希望納期を考慮しつつ、
納得してもらえる範囲でスケジュールを調整しましょう。
予算
要件定義書には、Webサイト制作にかかる費用も記載します。
次のように具体的に項目を書き出し、
それぞれの費用を記載するとクライアントも安心します。
- ディレクション費:Webサイト制作のプロジェクト進行管理費用
- サイト設計費:Webサイトの構造を決める際の費用
- デザイン費:Webサイトのデザインを決める際の費用
- コーディング費:デザインを実装するための費用
- コンテンツ制作費:記事執筆などコンテンツ制作にかかる費用
- 動作確認費:Webサイトが正しく動作するか確認する際の費用
Webサイト制作費用だけでは
どの工程でどの程度費用がかかるか把握できません。
クライアントが安心してWebサイト制作を依頼できるように、
工程ごとに予算を明記しておきます。
場合によっては、一部の工程は自社で対応したいなど
クライアントから要望が出てくる可能性もあります。
その際はクライアントと話し合いながら
どちらが対応するか決めましょう。
納品方法
納品方法についても要件定義書に明記することが重要です。
クライアントの要望を把握した上で
要件定義書に納品方法を反映させましょう。
Webサイトの一般的な納品方法は、以下の2種類あります。
- ファイルをZIP形式のフォルダに圧縮して納品
- ローカル環境でWebサイトを作成し、FTPソフトを介してサーバーに移行
納品方法を明確に定義することで、
制作したWebサイトを安全に譲渡できます。
また、納品後の運用やメンテナンスが容易になるので、
長期的な視点でもメリットがあります。
運用保守の有無
要件定義書には、Webサイトリリース後の運用や保守など、
アフターサービスについても記載しましょう。
主に記載するのは、以下の4つの項目です。
- 連絡手段:メール、電話、チャットツールなど
- 対応時間:平日の業務時間のみなのか、休日や夜間も対応するのか
- 対応内容:不具合の修正、コンテンツの更新、機能の追加、セキュリティ対策など
- バックアップとリストア:バックアップの頻度、保存先、リストアにかかる時間など
Webサイト公開までの契約の場合でも、
保証期間についての取り決めは要件定義書に
記載しておくことが重要です。
運用保守について要件定義書に記載することで、
Webサイト公開後のトラブルを未然に防ぎ、
長期的に安定したWebサイトの運用が可能になります。
Web制作の要件定義を行うときのポイント
Web制作の要件定義を行う際は、
以下のポイントを把握しておきましょう。
- ヒアリングを徹底する
- 具体的かつ詳細に記載する
特にクライアントと認識を合わせるためには、
具体的かつ詳細な数字の記載が必要です。
ヒアリングを徹底する
要件定義を行う際には、クライアントへのヒアリングが
重要な役割を果たします。
ヒアリングを効果的に行う際は、
以下の5W2Hを意識することをおすすめします。
- When(いつ):プロジェクトのスケジュール、時間に関する情報
- Where(どこで):プロジェクトの実施場所や対象範囲、場所に関する情報
- Who(だれが):プロジェクトに関わるステークホルダーや担当者、人に関する情報
- What(なにを):プロジェクトの目的や達成すべき目標、内容に関する情報
- Why(なぜ):プロジェクトの背景や理由、目的に関する情報
- How(どのように):プロジェクトの進め方や手段、方法に関する情報
- How much(いくらで):プロジェクトの予算や費用、金額に関する情報
ヒアリングの際に、これらの視点を意識して質問をすることで、
要件定義に必要な内容を漏れなく収集できます。
具体的かつ詳細に記載する
要件定義は、具体的かつ詳細に記載することが重要です。
要件定義の情報はプロジェクトの全体像を形作り、
関係者間の共通理解を深めます。
しかし、要件定義が抽象的で曖昧な内容になってしまうと、
後の工程で誤解やトラブルを招く恐れがあります。
そのため、要件定義を行う際は、数値やイメージなどを
具体的に記載するように心掛けましょう。
まとめ:要件定義をしっかりと行い、円滑にWeb制作を進めよう
Web制作を円滑に進めるためには、
要件定義をしっかりと行う必要があります。
クライアントの要望や具体的な数値を要件定義書に盛り込み、
関係者の間で認識のズレが起きないようにしましょう。
Web制作で収益を伸ばしていくためには、
日頃の案件を丁寧にこなしクライアントの信頼を
獲得していくことがとても重要です。
これからWeb制作を始めたい人や
今よりも収入を伸ばしたい人のために、
公式LINEでWeb制作に役立つ情報を発信しています。
Web制作で伸び悩んでいる人はお友達登録して、
案件に役立つ最新のWeb制作情報を獲得してください!
無料登録でプレゼント
筆者としが運営するWEB制作支援コミュニティの公式LINEでは、無料登録でプレゼントを複数手に入れることができます。興味がある方は下記よりご登録ください。
\ LINE登録はこちら /
プレゼントの例はこちら。
・有益情報が満載の動画が多数のYouTube『とし Web制作フリーランス育成コーチ 』
・あなたの性格タイプがわかり営業に活かせる『ソーシャルスタイル診断』
・案件獲得ができるようになる『案件獲得ロードマップ』
・副業、フリーランスで成功した人たちの成功インタビューを集めた『講座生実績』
など様々なコンテンツを提供中です。
ご興味ある方は、ぜひ確認してみてください。

\ LINE登録はこちら /
